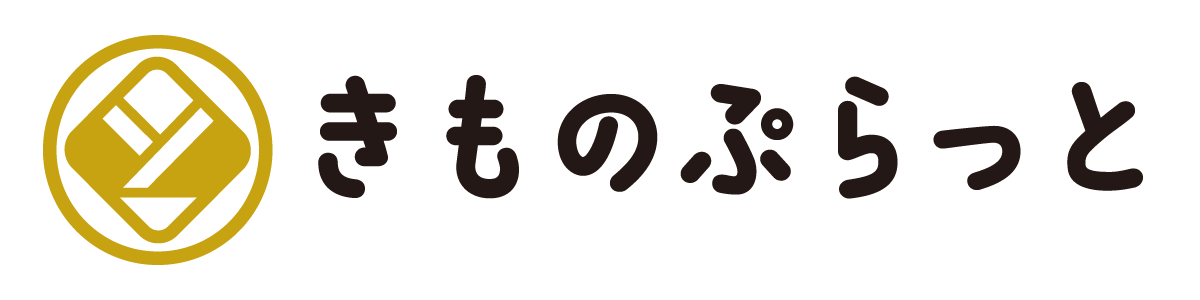「振袖一式の名称がわからない」「基本的な名称について押さえておきたい」といった方のために、振袖一式の名称を徹底解説!各部分の名称と役割のほか、振袖の着用シーンについてもまとめました。
初心者の方にもわかりやすいように、表やリストも交えて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
振袖一式の各部分の名称と役割
まずは、振袖一式に含まれる主な部分を表にまとめました。各部分の名称やその役割について詳しく解説していきます。
| 名称 | 役割・特徴 |
|---|---|
| 振袖 | お祝い事で着る未婚女性の第一礼装袖が長く厄払いの意味があり、華やかな着姿が特徴 |
| 袋帯 (ふくろおび) | フォーマルなシーンで使用される帯で、格式が高くお祝い事にぴったり |
| 帯締め | 帯の形が崩れないように押さえるためのもの華やかさをプラスしてくれるアイテム |
| 帯揚げ | 帯結びのときに使用するアイテム帯枕やその紐を隠し、整えるために使う |
| 伊達衿・重ね衿 | 振袖の半衿の上に挿す飾り衿顔周りに華やかさを加える |
| 長襦袢 (ながじゅばん) | 振袖の下に着る淡い色の着物着物の下に着用し、着心地を整える |
| 半衿 (はんえり) | 長襦袢の衿に縫い付ける布 |
| 衿芯 (えりしん) | 長襦袢の衿に入れて、襟部分の形を美しく保つためのアイテム |
| 補正パッド | 着姿を美しく見せるために、胸元や背中に入れて姿勢を整える |
| 足袋 (たび) | 和装用の白い靴下草履を履くために指先が分かれている |
振袖
振袖とは、成人式や結婚式などのお祝い事で着用される、袖の長い着物のこと。未婚女性の第一礼装であり、長い袖には厄除けやお清めの意味が込められています。
華やかな柄が特徴で、特に成人式で着用されることが多いです。
袋帯(ふくろおび)
振袖を着る際には帯も欠かせません。帯には「丸帯」や「名古屋帯」などさまざまな種類がありますが、成人式では「袋帯」を合わせることが一般的。
振袖の華やかさを引き立ててくれるので、式典にふさわしい装いに仕上がります。

帯締め
帯締めは本来帯の着崩れを防ぐためのものですが、現代ではコーディネートのアレンジに使用されることも多いです。
レースのものや装飾のついたものを合わせることで、豪華な雰囲気に仕上がります。
帯揚げ
帯揚げは、帯枕とセットで使うもの。帯枕を包み、外から見えなくなるようにするために使います。
着物と帯の間から少し除くので、デザインによってコーディネートの雰囲気を変えられます。
伊達衿(だてえり)・重ね衿
伊達衿(だてえり)は、長襦袢の襟の上に重ねて使う装飾用のアイテム。襟の部分に華やかさをプラスしたいときに使います。
長襦袢(ながじゅばん)
長襦袢は着物の下に着用するもので、洋服でいうインナーのようなものです。着物を汗や皮脂などから守ったり、着崩れの防止にもなります。また、冬場には防寒対策としても役立つアイテムです。
着物の袖口や襟、裾などからのぞくので、外から見えることがあります。着物を着用したときのバランスを考えて、色選びにもこだわると全身がおしゃれにまとまりおすすめです。
半衿(はんえり)
半衿(はんえり)は長襦袢の衿に付けて使用するもので、色やデザイン選びによって振袖の印象が変わります。成人式では、華やかな刺繍や絞りが施されたものが人気です。
衿芯(えりしん)
衿芯(えりしん)は長襦袢の衿に入れる「芯」として、衿をしっかり形作るために使われるもの。衿がきれいに決まるため、振袖姿が美しく引き立ちます。
補正パッド
補正パッドは、着付け時に体型を整えるために使用するものです。補正パッドを使うことで、着崩れやシワ、バランスの崩れを防ぎ、より美しいシルエットが作れます。
足袋(たび)
足袋(たび)は、着物に合わせる和装用の靴下です。草履(ぞうり)に合わせて、指先が分かれた作りになっているのが特徴。
冬の成人式では足元が冷えやすいので、暖かな素材のものを選ぶのがおすすめです。
振袖各部分の名称
続いて、振袖の各部分の名称をまとめました。着付けや振袖選びの際の参考にしてみてください。
| 名称 | 特徴 |
|---|---|
| 共衿 (ともえり) | 衿の上に重ねて使用し、着物が汚れないようにする本衿(地衿)の上に取り付けられている部分のこと |
| おはしょり | 着丈を帯の下あたりでたくし上げた部分のこと |
| 袖 (そで) | 振袖は長い袖が特徴。袖の長さやデザインによって華やかさが変わる |
| 袂 (たもと) | 袖の下部、袋状になった部分 |
| 身八つ口 (みやつぐち) | 振袖の脇部分にある縫い合わさっていない部分 |
| 上前 (うわまえ) | 着物を着たときに上に重なる部分 |
| 下前 (したまえ) | 上前の下に来る部分 |
| 衽 (おくみ) | 前幅を広くするために縫い付けた身頃の横にある部分 |
| 裾 (すそ) | 振袖の裾部分のこと |
| 褄先 (つまさき) | 衽の下の部分 |
| 衣紋 (えもん) | 衿の後ろ部分 |
共衿(ともえり)
共衿(ともえり)は襟の上に重ねて使うもので、着物が汚れないようにするためのもの。一般的に、本衿(地衿)の上に取り付けられています。
おはしょり
おはしょりは、着丈を帯の下あたりでたくし上げた部分のこと。明治時代中頃以降の女性特有の着物の着方です。
下の端をまっすぐなるように水平に整えて、人差し指の長さ程度の幅になるように作るのがちょうどよいとされています。
袖(そで)
袖は、振袖のなかでも腕を覆う部分のこと。振袖は長い袖が特徴で、袖の長さやデザインによって華やかさや格式が変わります。
袂(たもと)
袂は着物の袖全体の総称ですが、袖の下部分にある、袋状になった部分のことを指す場合が多いです。
身八つ口(みやつぐち)
身八つ口は、振袖の脇部分にある縫い合わされていない部分を指します。 女性や子どもの着物にのみあり、男性用の着物にはないのが特徴です。
江戸時代ごろ帯の位置はもっと上で締めていたものの、腕が動かしづらかったために作られたのが身八つ口の由来といわれています。
上前(うわまえ)
上前は、振袖を着た際に上に重ねる部分で、外側に来る部分のことを指します。着ている本人から見ると、左側にあたります。
下前(したまえ)
下前は上前(うわまえ)の反対で、振袖を着たときに下になる部分のことをいいます。本人から見て右側が下前です。
衽(おくみ)
衽は、振袖の左右の前身頃に縫い付けられている部分のこと。襟から裾まで続く、細長い半幅です。着付けの際には、おはしょりと衽が一直線になるように整えます。
裾(すそ)
裾は、振袖の裾部分のことです。下がすぼまるように着付けると美しい着姿になります。
褄先(つまさき)
褄先は衽の下の部分のことです。衿下と裾が交差する角の部分で、着付けの際には褄先を少し引き上げて、地面につかないように調整します。
衣紋(えもん)
衣紋(えもん)は後ろ襟の部分の名称です。襟を首の後ろ側に引いて、隙間を作ることを「衣紋を抜く」と表現します。
【一覧】小物類の名称と役割
以下に小物類の名称と役割についてまとめました。着付けの際に使用するアイテムや草履、バッグなどの小物類も押さえておきましょう。
| 名称 | 役割・特徴 |
|---|---|
| 伊達締め (だてじめ) | 着付ける際に腰紐を固定するためのアイテム振袖と長襦袢の着付けで使用する |
| 三重仮ひも | 帯の変わり結びを長時間キープするためのアイテム |
| 腰ひも | 着物を体にぴったりと合わせて固定するためのもの |
| コーリンベルト | 着付けの際に便利な小物。着物・長襦袢の襟を固定するために使われる |
| 前版 | 帯のシワを防ぐために、前太鼓に差し込んで使用する板 |
| 後板 | 帯の飾り結びを美しくキープするためのアイテム |
| 帯枕 | お太鼓の上の山形を整えるためのアイテム |
| 草履 | 振袖に合わせた和装向きの履物 |
| バッグ | 小物をまとめて持ち歩くのに必須帯地やエナメルなどさまざまな素材がある |
伊達締め(だてじめ)
伊達締めは、着付ける際に腰紐を固定するためのアイテムです。振袖と長襦袢の着付けで使用します。着崩れを防ぎ、美しい振袖姿を保つために欠かせません。
最近では、紐ではなくマジックテープタイプの「マジックベルト」も使われることが多く、スムーズに着付けができておすすめです。
三重仮ひも
三重仮ひもは、帯の変わり結びを長時間キープするためのアイテム。成人式や結婚式など_長時間のイベントでは特に重宝します。
用意が難しい場合は、ゴム紐やクリップなどで代用可能です。
腰ひも
腰ひもは着物を体にぴったりと合わせて固定するためのもので、「腰帯」とも呼ばれます。三重仮ひもや伊達締めとあわせてに使用することで、着崩れを防ぎます。
コーリンベルト
コーリンベルトは着付けの際に便利な小物で、着物・長襦袢の襟を固定するために使われます。着崩れを防いでくれるので、成人式など長時間着姿を美しく保ちたいときにぴったりです。
前版
帯のシワを防ぐために、前太鼓に差し込んで使用する板のこと。帯の種類や季節に合わせて、サイズや素材を使い分けるのがおすすめです。
後板
後板は、帯の飾り結びを美しくキープするためのアイテム。帯の後ろを固定するように、帯の背中に差し込んで使います。前版と比較すると色柄の種類は少ないのが特徴です。
帯枕
帯枕は、お太鼓の上の山形を整えるためのアイテムです。枕のような形をしているのが特徴で、帯揚の中に入れて使用します。
草履
草履は、着物に合わせた和装向きの履物です。バッグと合わせて振袖に似合う華やかなデザインのものを選ぶと、足元まできれいに仕上がります。
なお、草履は礼装にふさわしい履物ですが、成人式では草履だけでなく、ブーツを合わせたスタイルも人気です。
バッグ
小物をまとめて持ち歩くのに必須です。帯地やエナメルなどさまざまな素材のものがあるので、振袖のデザインや理想のイメージに合わせて選ぶのがポイント。
草履の鼻緒部分の柄と合わせると、より統一感のあるコーディネートにまとまります。
振袖の種類と着用シーン
振袖には袖の長さによって「大振袖」「中振袖」「小振袖」の3種類に分けられるのも特徴です。袖が長いほど格が高いとされ、「大振袖>中振袖>小振袖」の順で格付けされています。
| 振袖の種類 | 着用シーン |
|---|---|
| 大振袖 | 振袖の中で最も袖が長く、格式の高い振袖 婚礼衣装として着用される |
| 中振袖 | 袖丈は膝ぐらいまでの長さ 成人式・結婚式などで着用される |
| 小振袖 | 袖丈は身長の半分程度の長さ パーティーなどで気軽に着用される |
一般的に振袖というと、成人式や結婚式などで着用する「中振袖」を指すことが多いでしょう。
振袖の部品の名称に関するよくある質問
振袖の部品の名称に関するよくある質問をまとめました。
Q. 振袖の部品の名前は?
振袖の部品の名前は以下の通りです。
| 名称 | 特徴 |
|---|---|
| 共衿 (ともえり) | 衿の上に重ねて使用し、着物が汚れないようにする本衿(地衿)の上に取り付けられている部分のこと |
| おはしょり | 着丈を帯の下あたりでたくし上げた部分のこと |
| 袖 (そで) | 振袖は長い袖が特徴。袖の長さやデザインによって華やかさが変わる |
| 袂 (たもと) | 袖の下部、袋状になった部分 |
| 身八つ口 (みやつぐち) | 振袖の脇部分にある縫い合わさっていない部分 |
| 上前 (うわまえ) | 着物を着たときに上に重なる部分 |
| 下前 (したまえ) | 上前の下に来る部分 |
| 衽 (おくみ) | 前幅を広くするために縫い付けた身頃の横にある部分 |
| 裾 (すそ) | 振袖の裾部分のこと |
| 褄先 (つまさき) | 衽の下の部分 |
| 衣紋 (えもん) | 衿の後ろ部分 |
Q. 振袖の中に着るものの名前は?
振袖の中に着るもの「長襦袢(ながじゅばん)」です。振袖だけでなく、着物をきれいに着こなすための必須アイテムです。
Q. 成人式で使われるふわふわしたものの名前は?
成人式などで見かけるふわふわしたものは「ショール」です。冬の時期の寒さ対策になることはもちろん、振袖に華やかさをプラスしてくれます。
まとめ
振袖一式の名称について解説しました。振袖や着付けの際に使うアイテムにはさまざまな名前があるため、はじめは混乱してしまうかもしれません。
しかし、それぞれの名前を押さえておくと、振袖選びや着付けの際にスムーズです。ぜひ本記事を参考に、名称や役割を理解してみてください。