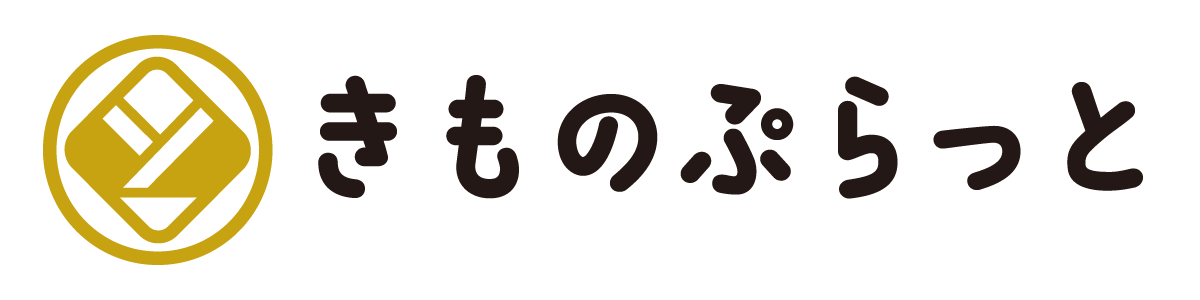「お宮参りに振袖を着てもいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。「お宮参り」は赤ちゃんにとって一生に一度のイベントであり、どんな服装で臨めばよいのか迷う方も多いでしょう。
本記事では、お宮参りでママ・パパ・赤ちゃんそれぞれにふさわしい和装の種類や、着物を着る際の注意点について詳しく解説します。
お宮参りに振袖は着用できる?

お宮参りにおいて、服装に明確なルールがあるわけではありません。ただし、ママも女の子の赤ちゃんも、振袖は着用しないことが一般的です。
振袖は未婚女性の第一礼装=ママは着用できない
振袖も和装の一種ですが、未婚女性の第一礼装です。出産を終えたママが振袖を着ることは、マナーの面でも控えた方がよいでしょう。
お宮参りの主役はあくまで赤ちゃん。両親は赤ちゃんよりも控えめな服装を心がけるのがマナーです。ママが着物を着る場合については後述しますが、訪問着や色無地、付下(つけさげ)など、落ち着きのある着物が好ましいといえます。
赤ちゃんは白羽二重の内着×祝い着が正装
お宮参りで赤ちゃんに和装をさせる場合は、「産着(掛け着・祝い着)」を身につけるのが一般的です。かつては、伝統的な正式スタイルとして「肌着の上から白羽二重(しろはぶたえ)と呼ばれる白い絹の着物を着用し、その上に産着を掛ける」という装いが主流でした。
この白羽二重は、赤ちゃんの晴れ着として格式ある装いとされていましたが、非常に高価であること、またお宮参り以外では着る機会が少ないことから、徐々に実用性が重視されるようになりました。
そのため近年では、白羽二重の代わりにベビードレスやカバーオールなどのベビー服を着せたうえで、産着を羽織らせるスタイルが定番となっています。男の子には鷹や兜、女の子には花や御所車などが描かれた華やかな柄が多く用いられます。
お宮参りでNGな服装は?

お宮参りは赤ちゃんの健やかな成長を願う大切な儀式であり、神社など格式ある場所で行うことが一般的。場にふさわしくない、カジュアルな服装は避けるべきとされています。
特にNGとされるのは、ノースリーブやミニ丈のワンピース、キャミソールタイプのトップスなど。肩や脚の露出が多いスタイルは、フォーマルな場には不適切です。夏場であっても、胸元が大きく開いたデザインや肌見せが多い服装は控えるのがマナーです。
【ママ】お宮参りに着用できる着物の種類

お宮参りでママが着物を着用する際は、控えめで上品な印象を与えるものを選びましょう。以下に、ママにおすすめの着物の種類を紹介します。
| 着物の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 訪問着 | 袖模様が着物全体に一続きで入った着物 |
| 色無地 | 一色で染められたシンプルな着物 |
| 付下 | 訪問着に似ているが柄が少し控えめ |
訪問着
訪問着は、フォーマルな場に対応できる格式のある着物で、肩から袖、裾にかけて絵羽模様が入っているのが特徴。
色柄も豊富で、華やかすぎず落ち着いたデザインを選べば、お宮参りにぴったりの装いに。家族の記念撮影でも品のよさが際立ちます。
色無地
色無地は一色で染められたシンプルな着物で、紋が入っていれば略礼装としても着用できます。淡いピンクや水色、ベージュなど、やさしい色合いを選ぶと、落ち着いた柔らかな装いになりおすすめです。
付下
付下は訪問着に似ていますが、柄が少し控えめなことが特徴。絵羽模様ではないためすっきりとしたデザインのものが多く、お宮参りのような改まった場にもふさわしいとされています。
【パパ】お宮参りに着用できる着物の種類
お宮参りでは、パパの服装も赤ちゃんとママの装いに合わせてフォーマルな装いに整えましょう。なお、赤ちゃんとママが和装を着用する場合でも、パパはスーツを選んでもOKです。
無地の着物×羽織
無地の着物に羽織を合わせた装いは、お宮参りにふさわしい和装スタイル。派手すぎず上品にまとまるため、赤ちゃんやママの装いとバランスをとりやすいのがメリットです。紋付きの羽織であれば、よりフォーマルな印象になります。
羽織袴
格式を重視するなら、羽織と袴を着用する羽織袴のスタイルもおすすめ。よりフォーマルな印象になります。一つ紋もしくは三つ紋入りのものを選びましょう。
スーツもOK
ママや赤ちゃんが和装でも、パパはスーツを着てもまったく問題ありません。ネクタイの色やポケットチーフなどで、柔らかく上品な印象にまとめると、着物姿のママや赤ちゃんとのバランスもとれます。
ダークスーツに白シャツ、落ち着いた色合いのネクタイを選ぶのが基本です。
【赤ちゃん】お宮参りにどんな祝い着を選べばいい?

お宮参りの主役である赤ちゃんは、祝い着(掛け着)を身にまとうのが伝統的なスタイルです。祝い着は内着(白羽二重やベビードレス)の上から羽織ります。
性別によって人気の色や柄に違いがあるため、女の子と男の子に分けて見てみましょう。
女の子の祝い着
女の子の祝い着では、赤やピンク、白などを基調とした明るく華やかな色合いが人気。
柄には、花や御所車、手毬、蝶など、可憐さや幸福、健やかな成長を象徴するモチーフが多く描かれます。
男の子の祝い着
男の子の場合は、黒や紺、深緑などの落ち着いた色が主流です。柄には、鷹、兜、松、龍などの縁起物が用いられ、「力強く、立派に育ってほしい」という願いが込められています。
祝い着には家紋を入れる場合もあり、祖父母から贈られる「初着」として特別な一着を用意する家庭もあります。
お宮参りで親が着るべき着物の色は?

お宮参りで着物を着る場合、色の選び方も大切なポイント。赤ちゃんが主役となる行事であるため、親は控えめで上品な色を選ぶことが基本とされています。
派手な色や目立つデザインは避け、落ち着いた印象にまとめるのがいいでしょう。
ママは淡い色合いがおすすめ
ママが選ぶ着物の色は、優しくやわらかい印象を与える淡い色合いがおすすめ。淡いピンク、クリーム、薄紫、水色、グレーなど、季節感や自分の肌色に合ったトーンを選ぶと自然になじみます。
特に春や秋のお宮参りでは、季節の花をモチーフにした上品な柄と淡い地色を組み合わせると、明るく清楚な印象に。反対に、濃い紫や真っ赤などの色は目立ちやすいため、避けるのが無難です。
パパは落ち着いた色がおすすめ
パパが着物やスーツを着る場合も、シンプルで落ち着いた色合いが基本です。黒や紺、グレーなどのダーク系カラーが選ばれる傾向にあります。
家族全体のバランスを考えたとき、ママや赤ちゃんの装いよりも控えめに見えることが大切です。スーツの場合も派手な柄のネクタイや明るすぎる色味は避け、シンプルかつ上品な雰囲気にまとめましょう。
お宮参りで着物を着用するメリット
お宮参りは赤ちゃんの誕生を祝う大切な行事。ここでは、そんなお宮参りに着物を着用するメリットを紹介します。
家族の大切な思い出になる
着物姿で撮影したお宮参りの写真は、何年たっても色あせない特別な記念になります。アルバムや記念品としても見栄えのいい仕上がりになるでしょう。普段なかなか着る機会のない着物だからこそ、特別感のある思い出を残せます。
あたたかいため、快適に過ごせる
着物は見た目の華やかさはもちろん、保温性が高いという実用的なメリットもあります。和装用の肌着や長襦袢、補正用のタオル、帯などを重ね着するため、寒い時期でもあたたかく過ごせるはずです。
特に冬や風のある日のお宮参りでは、洋服よりも着物の方が快適に感じられる場合もあります。
お祝いムードにぴったり
着物はフォーマルで華やかな装いなので、お祝いのシーンにぴったり。着物を身にまとうことで、気持ちも晴れやかになるはずです。神社の厳かな雰囲気とも相性がよく、お祝いムードをより一層高めてくれます。
お宮参りに行く際の注意点
お宮参りはフォーマルな行事ですが、赤ちゃんを連れて外出することになるため、服装や準備には配慮が必要です。着物での参拝を考えている場合は、以下のような点に注意しておきましょう。
- ママは締め付けのない着物を選ぶ
- 授乳は着付け前に済ませる
- 着物の格に気をつける
- 階段や段差に気をつける
- 着崩れしないように着付けする
- 赤ちゃんの寒さと暑さ対策を徹底する
- 赤ちゃんの着物を誰が用意するか確認する
ママは締め付けのない着物を選ぶ
出産から日が浅い時期のお宮参りでは、ママの体調が完全に戻っていないこともあります。帯や補正で締め付けすぎると体に負担がかかるため、着付けの際はできるだけ締め付けのない着物を選び、着付けの際に調整してもらいましょう。
授乳は着付け前に済ませる
授乳が必要な赤ちゃんを連れてのお宮参りでは、着物の着付け前に授乳を済ませておくのがベスト。着物を着たまま授乳をするのは難しいため、事前に調整しておいた方がスムーズです。
着物の格に気をつける
家族の服装は赤ちゃんの祝い着よりも控えめであることがマナーです。特にママの着物は、柄や色が華やかすぎないものを選び、アクセサリーも最小限にとどめるのが基本のマナーです。
階段や段差に気をつける
振袖はいつもの装いよりも裾が長く、歩幅が狭くなります。そのため、特に階段や段差での転倒には要注意。
神社の境内には階段や小さな段差が多く、気をつけて歩く必要があります。転びやすくなるので、ゆっくりと慎重に歩くことを心がけましょう。
着崩れしないように着付けする
お宮参りでは歩き回ることが多いため、着物の着崩れが起こりやすいです。特に行き帰りや、神社の中を歩くときには注意が必要。
着崩れが起こらないよう、着付けの際にはしっかりと補正を行い、帯の締め具合を確認してもらいましょう。
赤ちゃんの寒さと暑さ対策を徹底する
赤ちゃんは温度変化に敏感です。祝い着の下には季節に応じたインナーや肌着を重ねて調整しましょう。
夏場は通気性を重視し、冬場は体温を奪われないようにしっかり防寒を。外での行動時間をなるべく短くし、必要に応じてベビーカーやブランケットも活用しましょう。
赤ちゃんの着物を誰が用意するか確認する
祝い着の用意は、母方の祖父母が贈るのが慣習とされる地域もあります。ただし、現在では母方・父方どちらが準備しても問題なく、両家で相談して決める家庭が増えています。
直前に慌てないように、事前に「誰が、どんなものを用意するのか」を話し合っておきましょう。
赤ちゃん用着物の用意手段・相場
祝い着を購入する場合の相場は、2万〜5万円程度が一般的。生地の質や刺繍、家紋の有無によって価格は変動し、こだわると10万円を超えることもあります。「初着」として記念に残したい、兄弟姉妹にも使いたいという場合は、購入を検討するのもいいでしょう。
また、レンタルすることも可能です。レンタルの場合の相場は、5,000円〜15,000円程度と購入よりも費用を抑えられ、手軽に利用できるのがメリットです。オンラインショップや呉服店、写真スタジオなどで取り扱いがあります。
当日あると便利なアイテム
お宮参りの当日にあると便利なアイテムは以下の通り。お宮参りは写真撮影の機会も多いので、メイク直しや着崩れを直す際に重宝するアイテムをチェックしておきましょう。
| アイテム | 用途 |
|---|---|
| 大きめのクリップや洗濯バサミ(2〜3個) | トイレなどで役に立つ |
| 大きめのハンカチ(50cm以上) | 下を向いたときに化粧で汚れるのを防ぐ |
| 安全ピン・クリップ | 何かと便利 |
| 髪留め・ヘアピン | 髪が邪魔なときに役立つ・化粧直しのときにも便利 |
| 油取り紙・ミニミラー | 化粧直しに役立つ |
着崩れした際の直し方
着物の着崩れを直す際は、鏡を見ながら行うのが理想的。一人で直すのが難しい場合は、同行者に協力してもらいましょう。急激な動きは避け、ゆっくりとていねいに調整することがポイントです。
衿元が緩んでいる場合
衿元が緩んでいる場合の直し方は以下の通りです。
- 両手で衿を持ち、後ろに引いて衿を詰める
- 右衿を左に、左衿を右に引っ張り、交差させる
- 衿の交差位置が鎖骨の真ん中辺りになるように調整する
- 両手で衿を押さえながら、体を左右にねじって衿を落ち着かせる
身頃が下がっている場合
身頃が下がっている場合の直し方は以下の通りです。
- 両脇から振袖の身頃を持ち、上に引き上げる
- 腰の位置で振袖を持ち、身頃を上下に揺すりながら全体的に引き上げる
- おはしょりの量が適切になるよう調整する
- 身頃を引き上げて衿元や裾の乱れがないか確認し、必要に応じて調整
帯が下がっている場合
帯が下がっている場合の直し方は以下の通りです。
- 帯の両端を持ち、上に引き上げる
- 帯の位置が適切な高さ(通常はウエストのやや上)になるよう調整
- 帯揚げと帯締めも同時に引き上げ、位置を整える
- 帯結びの形が崩れている場合は結び目を軽く押さえたり引っ張ったりして調整
- 帯の下から振袖の身頃がはみ出していないか確認(はみ出している場合は中に入れ込む)
お宮参り・振袖に関するよくある質問
Q.お宮参りにかける着物を何と呼ぶ?
赤ちゃんが着用する祝い着は、「掛け着」または「初着(うぶぎ)」と呼ばれます。
Q.お宮参りの着物はなんでもいい?
赤ちゃんよりも両親の装いが目立たないようにすることが基本です。ママは訪問着や色無地、パパは無地の着物やスーツなど、控えめで上品な装いを選びましょう。
まとめ
お宮参りで振袖は基本的に着用されず、赤ちゃんは「白羽二重の内着×祝い着」、ママは訪問着や色無地などの控えめな装いが一般的です。
赤ちゃんが主役となる行事なので、家族は落ち着いた和装で晴れの日を迎えましょう。本記事を参考に、服装の選び方や注意点を押さえて、心に残るお宮参りを過ごしてみてください!